�@�P�P���Q�V���ɑ�Q���P�X�P��ڂ̊w�K������{���܂����B�O��A��P�́u��p���i�Ɨ����v�̍ŏI�i�����c���Ă��܂����̂ŁA�܂�������������܂����B���̂��Ƒ�Q�͂ɓ���A�R���̂P�قǐi�݂܂����B
��P�с@��]���l�̗����ւ̓]���Ə�]���l���̗������ւ̓]��
��P�́@��p���i�Ɨ����i�c��j
�i�ŏI�i���j
�v���[�h������]���l�i�����j�͗��ʂ��琶����ƍl���A�����s���`�ƍl����
�@��P�͂̏I���̂Ƃ���ŏ�]���l(����)�����ʉߒ����琶����ƍl������l�̌��������グ���Ă��܂��B�ŏ��̓g�����Y�ł����B�ŏI�i�����v���[�h�������グ���Ă��܂��B���̒i���́A�ނ̎咣�̔w�i��m��Ȃ��Ɨ������ɂ����Ƃ��낪����܂��B
�@�u���i�̔�p���i�͏��i�̌����̉��l���Ȃ��Ă���A��]���l�͏��i�����l�����������邱�Ƃ��琶����̂��Ƃ��������A���������āA���i�̔̔����i�����̔�p���i�ɓ�������A���Ȃ킿���i�ɔ�₳�ꂽ���Y��i�̉��i�E�v���X�E�J���ɓ�������A���i�͉��l�ǂ���ɔ�����̂��Ƃ��������A���̂悤�Ȗ��v�z�Ȍ������v���h���i�v���[�h���\���p�ҁj�͂����̊w�҂Ԃ������܂������ŎЉ��`�̐V�����������ꂽ�閧���Ɛ������Ă����̂ł���B���̂悤�ɏ��i�̉��l�����i�̔�p���i�ɋA�������Ă��܂��Ƃ������Ƃ́A���ۂɔނ̐l����s�̊�b���Ȃ��Ă���̂ł���v�iWEW�Ō���49�Łj�B
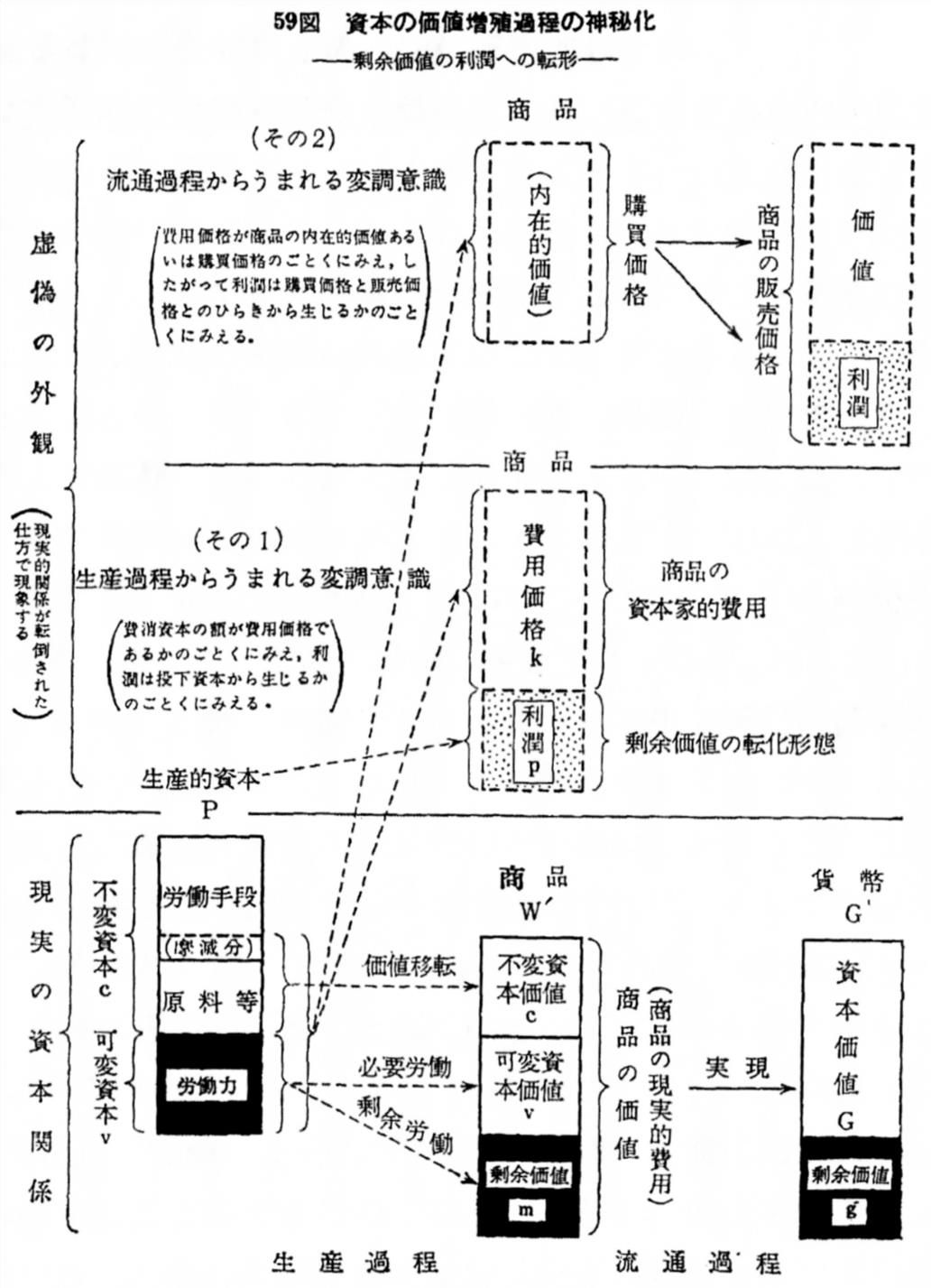
�s�z���M�O�Y�w�}�����{�_�x���t
�@���i�̌����I���l�i���ݓI���l�j�͏��i�ɓ������ꂽ�J���ʂȂ̂ł��B�Ƃ��낪�v���[�h���ɂ����ẮA���i�̔�p���i���������I���l�Ȃ̂ł��i�}��(���̂Q)�̂悤�Ȍ����ł��j�B��p���i�͏��i���Y�ɔ�₳�ꂽ���Y��i�ƘJ���͂��Ȃ킿�x�o���ꂽ���{���Ă镔���ł���Ƃ��Ă��A���i�̓��ݓI���l�ł͂Ȃ��̂ł����A���ꂱ���^���̉��l�ł����āA����ȏ�̉��i�ŏ��i�������邱�Ƃ͕s���i�s���`�j���Ɣނ͍l���܂����B�����ď��i����p���i�i�ނ̍l������ݓI���l�j�Ŕ����邱�Ƃ����z���Ƃ��܂����B�ނɂ��ƁA�g�ׂ��h�i��]���l�B�ނ͂���𗘎q�Ƒ����܂����j�͔̔��i���ʉߒ��j�ŏ��i���s���ɍ��������邱�Ƃɂ���Ċl�������̂�����A��p���i�Ŕ�����悤�l����s�����ʂ�g�D������Ηǂ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������͂̓v���[�h���̌����ƒ��ڊW���Ȃ��悤�Ɍ�����̂ł����A�P�[�X��z�肵�Ĕނ̌����������Ă���悤�ł��B
�@20�d�ʃ|���h�̎���30�V�����O�ŁA���̓����Y��i24�V�����O�A�J����3�V�����O�A��]���l3�V�����O���Ƃ��܂��B����20�d�ʃ|���h�̎���27�V�����O�i���̊z�͔�p���i�ɓ������j�Ŕ������ꍇ�A��]���l�͂ǂ��Ȃ�ł��傤���H
�@�u������͂Q�|���h�̎��������ł��炤���ƂɂȂ�A����������A���̏��i�͂��̉��l�����P�O���̂P�������������邱�ƂɂȂ�B�������A�J���҂���]�J���������Ƃ������Ƃɕς��͂Ȃ��̂ł����āA������������̎��{�ƓI���Y�҂̂��߂ɂł͂Ȃ����̔�����̂��߂ɂ����Ƃ��������̂��Ƃł���v�i49-50�Łj
�@���i���p���i�Ŕ����Ă���]���l�͖����Ȃ�܂���B��]���l�͔����łł͂Ȃ������肪�擾���邱�ƂɂȂ�܂��B�ł́A���ׂĂ̏��i����p���i�Ŕ�����Ƃǂ��Ȃ�ł��傤���H
�@�u���������ׂĂ̏��i�����ꂼ��̔�p���i�Ŕ�����Ȃ�A���̌��ʂ́A�����̏��i�����ׂĔ�p���i���������A���������ꂼ��̉��l�ǂ���ɔ���ꂽ�ꍇ�Ǝ����㓯���ł���ƑO�邱�Ƃ́A�܂������܂������ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A�J���͂̉��l�A�J�����̒����A�J���̍��x�͂ǂ��ł��������Ɖ��肵�Ă��A����ł��Ȃ��A���낢��ȏ��i��ނ̉��l�̂Ȃ��Ɋ܂܂�Ă����]���l�̗ʂ́A���ꂼ��̏��i��ނ̐��Y�ɑO�݂�����鎑�{�̗L�@�I�\���̑���ɂ��������Ĕ��Ɉ���Ă��邩��ł���v�i50�Łj
�@�������������O�ɁA�M�҂͖{���ɏo�ė��Ȃ��ʂ̃P�[�X���l���Ă݂܂����BA�Ƃ������Y�҂������̏��i���p���i�ła�ɔ���A���x�͋t�ɂa�������̏��i���p���i�ł`�ɔ���ꍇ��z�肵�܂��B�������҂̏��i�̉��l�\�����܂����������œ��z���Ƃ���Ȃ�A�`�́A�����̏��i�̔���ŏ�]���l�����A�����ła�̏��i�̏�]���l�����l�����邱�ƂɂȂ�܂��B����ɑ��a�́A�����̏��i�̔���ŏ�]���l�����A�����ł`�̏�]���l�����l�����܂��B���̌���ł́i���҂̊Ԃł́j�����㉿�l�ǂ���̏��i�������s�Ȃ�ꂽ�̂Ɠ������ƂɂȂ�܂��B����͎��{�Ɠ��m�����݂ɔ��������A���������̏��i�͓����ʂ̏�]���l���܂�ł���Ƃ�������ȃP�[�X�ł��B
�@���ׂĂ̏��i����p���i�Ŕ�����ꍇ�́A���l�Ɋ܂܂���]���l�̗ʂ͏��i��ނɂ���ĈقȂ�̂�����A���ꂼ��̏��i����p���i�Ŕ��������Ɓu���l�ǂ���ɔ���ꂽ�ꍇ�Ǝ����㓯���v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��A�J���͂̉��l�A�J�����̒����A�J���̍��x���������Ɖ��肵�Ă��������A�Ƃ����̂��}���N�X�̌����ł��B�Ȃ��Ȃ�u���ꂼ��̏��i��ނ̐��Y�ɑO�݂�����鎑�{�̗L�@�I�\���v���قȂ�A���̑���ɂ��������ď�]���l�̗ʂ��Ⴄ���炾�Ƃ����̂ł��B����͂ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA��L�R�_�������ł����Ă��A�L�@�I�\���͗l�X�ł��蓾��̂������]���l�̗ʂ��l�X�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��i����͌X�̎��{�Ƃɂ��Ă����邱�Ƃł����āA�Љ�S�̂ł͏�]���l�̑��z�͓����ɂȂ�Ǝv���܂��j�B�����ɒ�8������A��P����X�͂̕��͂����p����Ă��܂��B���̒i�K�ł͗L�@�I�\���̓e�[�}�ɂȂ��Ă͂��炸�A���̕����̒��Ƃ��Ă͈�a��������܂��i����̓G���Q���X���t�������Ȃ̂ł��傤���H�j�B
�@�ǂ�ȏꍇ�ł���]���l�i�����j�͐��Y�ߒ��Ō`�������̂ł���A���ʏ�̑���ɂ���Ė��������Ƃ͂ł��܂���B�v���[�h�����l����s�̍\�z�͗��ʏ�̑���ɂ���ė�������苎�邱�Ƃ��ł���Ƃ������z�Ɋ�Â��Ă��܂��B�Ȃ��A�v���[�h���̌����Ǝ��H��m�邤���ŁA�Ó��z�q���̘_���w�v���[�h���M�p�_�̓W�J�x�i�l�b�g����_�E�����[�h�\�j���Q�l�ɂȂ�܂��B����������Γǂ�ł݂Ă��������B
��Q�́u�������v�i�O���j
�@����Ƒ�Q�͂ɓ���܂����B��P�͂̎c��Ɉ��̎��Ԃ��₵�����Ƃ������āA�i�̂͂R���̂P�قǂł����B
�@��Q�͂́A��v���e�i��P���e�j�������Ă��܂��B����̓G���Q���X�̏����ɂ���܂��B
���{�Ƃ́A��]���l�͐��Y�ɗv�������ׂĂ̐��������l�ɐ�����ƊϔO����
�@�u���{�Ƃ����i�Y����̂́A���̏��i���̂��̂̂��߂ł��Ȃ���A���̏��i�̎g�p���l�܂��͂��̎g�p���l�̌l�I����̂��߂ł��Ȃ��B���{�ƂɂƂ��Ď��ۂɖ��ɂȂ鐶�Y���́A��ł��߂鐶�Y�����̂��̂ł͂Ȃ��A���Y���̉��l�̂������̐��Y���ɏ���ꂽ���{�̉��l���z���钴�ߕ��ł���v(����51��)
�@�u���Y���̉��l�̂������̐��Y���ɏ���ꂽ���{�̉��l���z���钴�ߕ��v�̊l���������{�Ƃ̎���ړI���Ƃ������Ƃł��B�u���{�Ƃ͑����{���A����̂��낢��Ȑ�������]���l�̐��Y�ʼn���������̑�����ڗ����邱�ƂȂ��ɁA�O�݂�����B�ނ͂����̐��������ׂĈ�l�ɁA�P�ɑO�ݎ��{���Đ��Y���邽�߂����ł͂Ȃ��A�O�ݎ��{���z���鉿�l���ߕ��Y���邽�߂ɁA�O�݂��v�i���O�j����Ƃ����̂ł��B
�@�{�ł͂Ȃ��̂ł����A�u���̏��i�̎g�p���l�܂��͂��̎g�p���l�̌l�I����̂��߂ł��Ȃ��v�Ƃ��������̈Ӗ��ɂ��Ď�̋c�_������܂����B���{�Ƃ͎g�p���l�̐��Y�ɑ��Ă͂����������Ƃ��Ƃ��������Ƃł͂Ȃ��i�����������{�Ƃɂ͂����������ʂ�����ɂ��Ă��j�A�����ł͏���ɋ������L�p���ł��邱�Ƃ͑O��ł����āA�g�p���l�͏]���I�Ȍ_�@�ł����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ������Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂����i�g�p���l�͉��l�܂��͏�]���l�̒S����ł���Ƃ̔���������܂������A���̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��j�B
�@�}���N�X�́A���{�Ƃ���]���l�̌������Ȃ������{�̑O�݂ɋ��߂Ă��邩�𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ��Ă��܂��B
�@�u�ނ́A�������O�݂�����ώ��{�̉��l���A�����A������Ă���J���ƌ������邱�Ƃɂ���Ă̂݁A�����Ă���J������悷�邱�Ƃɂ���Ă̂݁A���傫�����l�ɓ]�������邱�Ƃ��ł���v�̂ł����A���̂��߂ɂ͓����Ɂu���̘J���̎����̂��߂̏������A���Ȃ킿�J����i��J���ΏہA�@�B�⌴����O�݂��v���Ȃ���Ȃ�܂���B�u���Ȃ킿�A�����������Ă��鉿�l�z�Y�����̌`�Ԃɓ]��������v�A�܂�J���͂Ɛ��Y��i�Y�ߒ��Ō���������K�v������܂��B�u���������ނ����{�Ƃł���̂́A�܂��A���������J���̍��ߒ�����Ă邱�Ƃ��ł���̂́A�����A�ނ��J�������i���e�́u���Y�������v�j�̏��L�҂Ƃ��ĒP�Ȃ�J���͏��L�҂Ƃ��Ă̘J���҂ɑ����Ă��邩��v�i���O�j�ł��B
�@�����Ŗ��ɂȂ�̂́A�O�݂�����s�ώ��{�i���Y��i�j�Ɖώ��{�i�J���́j�Ƃ̊W�ł����A���{�ƂɂƂ��Ă͉ώ��{���s�ώ��{���������E��l�ɉ��l���B�Ɋ�^����Ǝv�����ގ���ȉ��̂悤�ɐ�������Ă��܂��B
�@�u���{�ƂɂƂ��ẮA�����͉ώ��{���痘�����������������߂ɕs�ώ��{��O�݂�����̂��Ƃ����悤�Ɏ��������邩�A����Ƃ��s�ώ��{�B���邽�߂ɉώ��{��O�݂�����̂��Ƃ����悤�Ɍ��邩�A���Ȃ킿�A�@�B�⌴���ɂ��傫�����l��^���邽�߂ɉݕ���J���ɓ�����̂��ƌ��邩�A����Ƃ��J������悷�邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��邽�߂ɉݕ����@�B�⌴���ɑO�݂�����̂��ƌ��邩�́A�ǂ���ł����܂�Ȃ��̂ł���B���{�Ƃ͂����s�ώ��{��O�݂����邱�Ƃɂ���Ă̂ݘJ������悷�邱�Ƃ��ł���̂�����A�܂��ނ͂����ώ��{��O�݂����邱�Ƃɂ���Ă̂ݕs�ώ��{�B���邱�Ƃ��ł���̂�����A�ނɂƂ��Ă͂����̂��Ƃ͊ϔO�̂Ȃ��ł݂͂ȓ������ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł���A�������A�ނ̗����̌����̓x�����͉ώ��{�ɂ������銄���ɂ���Ăł͂Ȃ������{�ɂ������銄���ɂ���āA���Ȃ킿��]���l���ɂ���Ăł͂Ȃ��������ɂ���ċK�肳��Ă���A���̗������͂��ƂŌ���悤�ɂ��ꎩ�g�͓����܂܂ł����낢��Ɉ������]���l����\�킷���Ƃ��ł���̂�����A�܂��܂������Ȃ�̂ł���v�i52�Łj
�@�s�ώ��{�Ɖώ��{�A���̂ǂ��炪�����Ă����l�𑝂₷���Ƃ��ł��Ȃ��̂�����A���{�ƂɂƂ��Ă͂ǂ���������悤�Ȃ��̂��Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��B���̗�����O�݂����č��̂����͎̂����ł���A�����痘���͂��̕�V���Ƃ�����ł��i�����ł͂����������Ƃ͏�����Ă��܂��j�B
�@�Ō�̈ꕶ�́u�������v�ȍ~�̑O�������Ɂu�ނ̗����̌����̓x�����͉ώ��{�ɂ������銄���ɂ���Ăł͂Ȃ������{�ɂ������銄���ɂ���āA���Ȃ킿��]���l���ɂ���Ăł͂Ȃ��������ɂ���ċK�肳��Ă���v�Ƃ���܂��i�u�������v�Ƃ������t���o�Ă��܂����A�T�O�K��͂��̐�łȂ���Ă��܂��j�B���̋L�q�����ϗ������̌`���i��X�́j���O���ɒu����Ă���悤�Ɏv���܂��i���ϗ��������`�������Ǝ��ۂɂ���ɂ���ė����i�����j���Ĕz������邩��ł����A��̘b�Ȃ̂Ō��߂��邱�Ƃ����܂���ł����j�B�����A�㔼�����́u���̗������͂��ƂŌ���悤�ɂ��ꎩ�g�͓����܂܂ł����낢��Ɉ������]���l����\�킷���Ƃ��ł���v�́u���Ɓv�͎��́i��R�́j�̂��Ƃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂����B
�u���ߕ��v�͓�̌`�ŕ\�킳�꓾��\�\�@���i���l�̂����̔�p���i���z���钴�ߕ��Ƃ��āA�A�O�ݑ����{���z���钴�ߕ��Ƃ���
�@�u���i�Ɋ܂܂�Ă��鉿�l�́A���i�̐��Y�ɔ�₳���J�����Ԃɓ������A�܂����̘J���̑��ʂ͎x���J���ƕs���J���Ƃ��琬���Ă���B����ɔ����āA���{�ƂɂƂ��Ă̏��i�̔�p�́A���i�ɑΏۉ�����Ă���J���̂����̔ނ̎x�����������������琬���Ă���B���i�Ɋ܂܂�Ă����]�J���́A�J���҂ɂ͎x���J���Ƃ܂����������ɘJ�����₳����ɂ�������炸�A�܂��x���J���Ƃ܂����������ɉ��l��n�������l�`���v�f�Ƃ��ď��i�ɂ͂���ɂ�������炸�A���{�ƂɂƂ��Ă͂Ȃ�̔�p��������Ȃ��̂ł���B���{�Ƃ̗��v�́A�������㉿���x�����Ă��Ȃ����̂邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��琶����B��]���l�܂��͗����́A�܂��ɏ��i���l�����i�̔�p���i���z���钴�ߕ��Ȃ̂ł���B���Ȃ킿�A���i�Ɋ܂܂�Ă��鑍�J���ʂ����i�Ɋ܂܂�Ă���x���J���ʂ��z���钴�ߕ��Ȃ̂ł���B������A��]���l�́A���ꂪ�ǂ����琶�܂��ɂ���A�Ƃɂ����O�ݑ����{���z���钴�ߕ��ł���v�i52�Łj
�@�ŏ��̈�s�ŁA���i�̉��l�͂��̐��Y�ɔ�₳�ꂽ�J�����Ԃɓ������Ƃ��������ŁA�u���̘J���̑��ʂ͎x���J���ƕs���J���Ƃ��琬���Ă���v�ƌ��������Ă��܂��B��P���ł͎x���J���ƕs���J���Ƃ����͕̂K�v�J���Ə�]�J���̒ʑ��I�\�����Ƃ���܂��B�܂��J�����ɐV���ɕt��������ꂽ�J���̂����̓�̕����ł��B���������i���l�ɂ͂��̂ق��ɏ���ꂽ���Y��i�̉��l�i�ړ]���l�j�ɑ�������J�����܂܂�Ă���͂��ł��B���̕����͂ǂ��ɍs���Ă��܂����̂ł��傤���H�@�ӎ��I�Ɏ̏ۂ��Ă���̂ł��傤���H�@�ł��������͂́u���{�ƂɂƂ��Ă̏��i�̔�p�́A���i�ɑΏۉ�����Ă���J���̂����̔ނ̎x�����������������琬���Ă���v�Ƃ���܂��B�u���{�ƂɂƂ��Ă̏��i�̔�p�v�Ƃ͔�p���i�ɑ��Ȃ炸�A���{�������ł��i���͑��Ղ����s�ώ��{�j�B�����ł͂��������x���J���ʂɉ������Ă���Ƃ����̂����R�ł��B��p���i���x���J���ʂ��Ƃ���Ă���A���������ď�]���l�܂��͗����́u���i�Ɋ܂܂�Ă��鑍�J���ʂ����i�Ɋ܂܂�Ă���x���J���ʂ��z���钴�ߕ��v���Ƃ������ƂɂȂ�܂��i���j�B
���x���J���E�s���J���Ƃ����敪�͍��W��\�����邽�߂ɏd�v�ł��B��P���ł̎g�p�@���{���Ǝv���܂��B
�@���āu��]���l�܂��͗����v�͓�ʂ�ɕ\�킳��Ă��܂��B��́u���i���l�����i�̔�p���i���z���钴�ߕ��v�Ƃ��āA������́u�O�ݑ����{���z���钴�ߕ��v�Ƃ��āA�ł��B���҂̈Ⴂ�́A����������A�������̗ʁi��]���l�܂��͗����j�ƑΔ䂳�����̂��Ⴄ���Ƃ��痈�Ă���ɉ߂��܂���B
�������͑����{�Ōv��ꂽ��]���l�̗����Ȃ킿��/�b����/(���{��)�ł���
�@�u�O�ݑ����{���z���钴�ߕ��v�̒��x�͂ǂ̂悤�ɕ\�����ł��傤���B
�@�u���̒��ߕ��͑����{�ɂ������Ă�/�b�Ƃ��������ŕ\�킳��銄�����Ȃ��Ă���̂ł���B���̂b�͑����{���Ӗ�������̂ł���B�������āA�����͏�]���l����/���Ƃ͕ʂ��̂ł��闘������/�b����/(���{��)��̂ł���v(52��)
�@�������Ƃ͉��������m�Ɏ�����Ă��܂��B��]���l�̑O�ݑ����{�ɑ��銄���ł���A�ƁB
�@�����ŋ^�₪�N���Ă��܂��B�����قǏ�]���l�͔�p���i���z���鏤�i���l�̒��ߕ��Ƃ��Ă��\�킳��Ă��܂����B������̗p����ƁA���̒��ߕ��͂�/��(��p���i)�Ƃ����悤�ɕ\�킷���Ƃ��ł��܂��i�������p���i�������ƌĂт����Ǝv���܂��j�B���Ήp�l���́A��R�����e�ɂ͂��̂悤�Ȍv�Z���@�����o�����Ə����Ă��܂��i�_���w��p���i�Ɠ��ނ̗������\�w���{�_�x��O�����͂̏����e�ɂ��āx���V��w�o�ϊw�_�W��48��4���j�B�Ƃ͂����������́u��]���l�̑O�ݑ����{�ɑ��銄���v�i����������{�������ƌĂт܂��j�Ɏ����Ă���悤�Ɋ������܂��B�ǂ����Ăł��傤���H�@��P�͂Ŗ��炩�ɂ��ꂽ�悤�ɁA��p���i�͎x�o���ꂽ���{���l�����i���l�ɍČ��������̂ł���A���������Ă��̎��{���Ă镔���ƌ��Ȃ���Ă��܂��B���{�Ƃɂ����ẮA�x�o����鎑�{�͎��{�ƂɂƂ��ĒP�Ȃ��p�ł����ď�]���l�̌����Ƃ��Ă͊ϔO����܂���B����ɌŒ莑�{���������{�Ɠ��l�ɐ��Y�ߒ��ɂ͂��ׂē��荞�ނƂ�����������܂��B���{�Ƃ́A�[�p�������{�̂��ׂāi���O�ݎ��{�j����]���l(����)�̌������ƍl����̂ł��B����͗���������/�b�Ƃ���v�Z���@�Ƀn�b�L���ƌ����Ă��܂��B
�u��]���l���̗������ւ̓]�������]���l�̗����ւ̓]���������o�����ׂ��ł����āA���̋t�ł͂Ȃ��v�Ƃ��H
�@�u�ώ��{�Ōv��ꂽ��]���l�̗��͏�]���l���ƌĂ�A�����{�Ōv��ꂽ��]���l�̗��͗������ƌĂ��B���̓�̗��́A�����ʂ��̈�����d���Ōv�������̂ł����āA�ړx������Ă��邽�߂ɓ����ɓ����ʂ̈���������܂��͊W��\�킷�v(53��)���Ƃ܂��āA�}���N�X�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�@�u��]���l���̗������ւ̓]�������]���l�̗����ւ̓]���������o�����ׂ��ł����āA���̋t�ł͂Ȃ��B�����āA���ۂɂ������������j�I�ȏo���_�ɂȂ�̂ł���B��]���l�Ə�]���l���Ƃ́A���ΓI�ɁA�ڂɌ����Ȃ����̂ł����āA�T������Ȃ���Ȃ�Ȃ��{���I�Ȃ��̂ł��邪�A�������́A���������Ă܂������Ƃ��Ă̏�]���l�̌`�Ԃ́A���ۂ̕\�ʂɌ����Ă�����̂ł���v(���O)
�@��i�̈�A��s�ڂ̉��߂��߂����Ĉ��̋c�_������܂����B�s���߂�����̂ł����A���̂悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ�܂����B
�@�O�i���ŏ�]���l���Ɨ������Ƃ͉��Ȃ̂�����������Ă��܂��B�����͓������ߕ��������ʁi���́j��������ړx�ł͌v���������܂��͊W�ł���A�ƁB��]���l�����������͓̂����Ȃ̂ŁA���̎��̂����������璭�߂Ă����҂̈Ⴂ�����o�����Ƃ͂ł��܂���B������ړx�Ă邱�Ƃɂ���ď�]���l�Ɨ����Ƃ̈Ⴂ�������Ă���̂ł��B�����ł́g���h���Ȃ킿�W����g���́h�̊T�O�������o�����ׂ����Ƃ������Ƃ������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@����ɓ���̂́A�������͂́u���ۂɂ������������j�I�ȏo���_�ɂȂ�v�̈Ӗ��ł��B�O���͗��_��̖��ł������A���̂��Ƃ͗��j�I�ɂ����Ă͂܂�ƌ����̂ł��B���������o���_���Ƃ������Ƃ́A���̂��̂ɐ�s����Ƃ������Ƃł��B�ł͉��ɑ��Đ�s����̂ł��傤���H�@�������́A��]���l���E��]���l�̂ǂ���Ƃ���r����Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�Ȃ��Ȃ�A�������͂ɂ���悤�ɁA��]���l�́u���ΓI�ɁA�ڂɌ����Ȃ��v���̂ł����āA���j�̕\�ʂɂ͌����Ȃ�����ł��i���ہA���l���ߕ�����]���l�Ƃ��Ė{���I�ɔc�������̂̓}���N�X�����߂Ăł��j�B�������Ɨ�������r����Ă��āA�������͗����ɗ��j�I�ɐ�s����Ƃ������Ƃ������Ă���̂ł��傤���H�@�������Ɨ����͕s���ł����āA���ԓI�ɑO��W������Ƃ����̂͊�Ȋ��������܂��B�������A���l���{���o�ꂵ�A���̂��ƂŎY�Ǝ��{����������Ƃ������j�I���������ɂȂ��炦�Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ̈ӌ���������܂����B���̗����͎��̂悤�Ȃ��̂ł��B���l���{�͗����ݏo���Ȃ��̂ł����A���l�͒��ړI�Ȍ𗬂̂Ȃ������̂Ⓖ�ړI���Y�҂Ƃ̊Ԃɗ����A�ނ�̐��Y���蔃�����邱�Ƃɂ���č��z�𗘏��Ƃ��Ċl�����܂��B���l�̊S�͂��̍��z�i���Ɨ����j�Ɍ������Ă��܂��B���̒i�K�̏��l���{�͎Y�Ǝ��{�̑��݂�O�Ă��܂���B���l���{�̊S�ƍs�������́A���z�̔������i�ɑ��銄�����Ȃ킿�������ł��B����ɑ��Č㑱�̎Y�Ǝ��{�͗����i���́j���̂��̂Y���܂��B�Y�Ǝ��{���`�������ƎY�Ǝ��{���D���ɂȂ�܂��B���l���{�𗘏����A�Y�Ǝ��{�𗘏��ɏے�������Ȃ�A�������˗����Ƃ�������ɂȂ�܂��B�M�҂́A�������̂悤�ȉ��߂ɂ͖���������Ɗ������̂ł����A��������蓾��悤�Ɏv���Ă��܂����B�L�͂ȉ��߂Ƃ��ďЉ�܂����B
�X�̎��{�Ƃ́A���{�̏������Ɖ��l���ߕ��Ƃ̂������̓��I�֘A�ɊS�������Ȃ�
�@�u�X�̎��{�Ƃɂ��Č����A�ނ��S�����B��̂��̂́A���i�̐��Y�̂��߂ɑO�݂����������{�ɂ��������]���l�́A�܂��͎����̏��i���ē����鉿�l���ߕ��́A�������Ƃ������Ƃ͖��炩�ł���B�����A���{�̓���ȏ������ɂ������邱�̒��ߕ��̓���̊����ɂ��A�܂����̏������Ƃ��̒��ߕ��Ƃ̓��I�Ȋ֘A�ɂ��A�ނ͂����S�������Ȃ������ł͂Ȃ��A�ނ���A���̓���̊����₱�̓��I�Ȋ֘A�ɂ��Ă͎����̖ڂ�����܂����Ƃ̂ق����ނ̊S���Ȃ̂ł���i�ނ̗��v�Ȃ̂ł���\�V���{�o�Ŗ�j�v(���O)
�@����ɓ��ɂ������邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B���̂��ƁA���l���ߕ��̎��������ʉߒ��ōs�Ȃ��A���������̎����̓x���������ʉߒ��̏�����┄���̋삯�����Ȃǂɍ��E����邱�Ƃ���A�X�̎��{�Ƃɂ����ẮA���ߕ������ʉߒ��Ō`������邩�̂悤�ȊϔO��������Ƃ��������Ƃ�����Ă��܂��B����ɐ��Y�ߒ��Ɨ��ʉߒ��Ƃ̗��ݍ����̖��ɘb���ڂ�̂ł����A�����Ŏ��Ԑ�ɂȂ��Ă��܂��܂����B
����i�P�Q���Q�T���j�͂��̑����i��X�i���j����ɂȂ�܂��B��Q�͎͂���œǂݏI�������ƍl���Ă��܂��B
�i��j

|